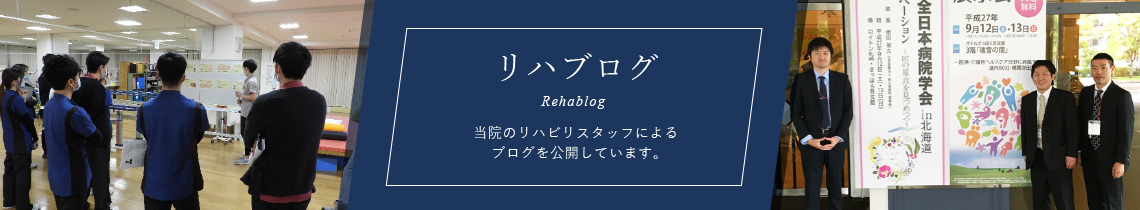カテゴリー: リハブログ
第10回 日本訪問リハ・・・
2017年06月19日
6月3日(土)から2日間に渡り、札幌で第10回 日本訪問リハビリテーション協会 学術大会が行われました。今回はシンポジウムの座長として参加させていただきました。
南は沖縄からの参加者もおり、全国各地の様々な方々との貴重な情報共有の機会となりました。
私が担当したシンポジウムでは、石川県加賀市の方と、青森県八戸市の方に協力をいただきました。当日に向けてはほぼメールのみでのやり取りで、企画の段階で苦労することもありましたが、とても貴重な出会いとなりました。
人口規模や地域資源の多寡などにより抱える課題は違うけれども、セラピストとして持つべき視点や考え方など、多くの共通事項があることも確認することが出来ました。今回の企画に推薦して下さった実行委員の方に感謝すると共に、またこのような機会に参加できるように地域貢献を続けたいと思います。
リハビリは訓練室だけに留まらない!
2017年06月08日
新年度が始まって早くも2ヶ月が経過しました。4月に新入職員が仲間に加わり、勢力を拡大し続けるリハビリテーション課は、質の高いリハビリテーションサービスの提供を目指すべく、日々奮闘しております。
さて、今回は今年度から始動するリハビリテーション課の新たな取り組みについてご紹介します。当院では以前より患者様に合わせたリハビリテーション提供の一環として、院外リハビリテーションについての起案を立ち上げ、ついにマニュアルが完成し今年度から始動する運びとなりました。今回ご紹介する方は、入院前からパン屋の仕事をされており、退院後も引き続き仕事を続けたいとのご要望を受け、我々スタッフは患者様とご家族様の協力のもと、病院から足を伸ばして仕事場にお邪魔しました。実際に作業する様子を再現していただくと、訓練室とは違う機敏な動きが見られたそうです。実際の仕事場という環境、道具を扱う感触などをきっかけに、長年染み付いた行為が潜在能力として呼び起こされた可能性があります。
このようなリアルな行為を再現できる状況を提供することで、患者様は手応えを感じ、それが自信に繋がり、入院中に抱いていた退院後の不安なども取り除くことができるのではないでしょうか。さらには、モチベーションが上がることで自己効力感が高まり、自然治癒力を活性化することにも繋がると考えます。新たな取り組みとして始動して間もないですが、皆様に満足していただけるよう、そして、今後さらなる発展と活動の幅を広げていけるよう、スタッフ一同頑張って参ります!本画像の投稿につきましては、ご本人様ならびにご家族様よりご了承いただいております。スタッフ一同、心より感謝申しあげます。
(リハビリテーション課 理学療法士主任 渡邉)
リハ課!新しい仲間と始動!
2017年04月24日
雪が溶けて少しずつ春の兆しがちらほらと感じられるようになってきました。今年も西堀病院に新しい仲間が増えました。理学療法士3名、作業療法士4名、言語聴覚士2名です。当院リハビリテーション課は通所リハ、訪問リハスタッフも合計すると、なんと……………総勢80名となりました!
数年前までは若年者の多かったリハビリテーション課も少しずつアラサー世代(30歳以上)が増えて参りました。少しずつ経験を積み重ねたスタッフの知識・技術と、新しい仲間たちの新鮮さと勢いを追い風にして今年度も患者様、利用者様を第一に考えリハビリテーションを提供していきたいと思っております。今年度もよろしくお願いいたします。
(文:理学療法士係長 佐藤)
備えあれば憂いなし~護身術訓練~
2017年02月10日
仕事はじめ
2017年01月18日
 明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年もリハ課ブログを随時更新していきたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。先日は1月11日鏡開きということで、お餅を食べられた方も多いかと思います。私もその一人ですが、お餅を食べながら、ふと、鏡開きの由来は何だろう?と疑問に思ったため少し調べてみました。
鏡開きとは、室町時代から武家で20日に行われており、武士は初柄(はつか)、婦人は初顔 (はつかお)、それぞれ最も重視している道具へのお供えと20日(はつか)との語呂合わせを祝っていたようです。徳川家光の忌日が20日であることから、江戸時代に11日に繰り上げられたとのことで、今では正月の終わり、または蔵開き、一般的には仕事始めとして広く認知されているようです。まだまだ正月ぼけから目覚めておりませんでしたので、11日を仕事始めと気持ちを切り替え、仕事に集中していきたいと思います!といった矢先の大寒波!!!
寒さと大雪に負けず、在宅でお待ちになられているご利用者様のためにも、頑張って訪問リハビリテーションを提供してまいります!
(文:訪問リハビリテーション西堀主任 畠山)
リハビリテーション課で勉強会を行いました!
2016年11月15日
ユニバーサルデザイン?自助具?ってなに?
2016年11月15日
こんにちは。11月を迎えて急に気温が下がり、とうとう函館にも雪が降りましたね。私も朝起きて、窓の外が真っ白になっているのを見て驚きました。皆さん、タイヤ交換はすでにお済ですか?私は雪が降る前の週にタイヤ交換をしていたのでぎりぎり間に合いましたが、職場の人から聞いた話によると雪が降った日のガソリンスタンドはタイヤ交換を待つ人で混雑していたそうです。
そして雪が降って大変な事と言えば、除雪です。私の地元は雪が多く、朝腰が埋まるぐらいまで降り、除雪をしても、夜になると同じくらい積り、また除雪をしなければなりません。最近、両親から「身体の節々が痛い。」と聞いているので除雪は大丈夫かな?と心配しています。そこで今年はユニバーサルデザインのスコップを買って、実家に送りました。このスコップは柄がS字に曲がっている事で除雪する時に腰へ掛かる負担を軽減し、除雪が随分と楽になるようです。
この様なユニバーサルデザインと呼ばれる道具を皆さんは知っていますか?また、他にも自助具と呼ばれる道具が有りますが、その違いは何か知っていますか?ユニバーサルデザインとは「すべての人にとって使いやすいデザイン」とされており、自助具やバリアフリーは「高齢者や障害を持つ人にとって使いやすいデザイン」とされています。身近なユニバーサルデザインの写真1はコードの先がマグネットになっていて、引っ掛かってもすぐに外れるので、ポットが倒れて、怪我や火傷などの事故につながりにくくなっています。写真2の自助具は西堀病院でも利用しており、手が不自由な方にとって箸やスプーンが持ちやすい形となっており、食器も倒れにくくて掬い易い形状をしています。そして実際にこれらを使ってみると便利なものが多くあります。皆さんもぜひ今回紹介したスコップなどの道具を体験し、安全な生活を過ごしてください。
(文:作業療法士主任 水越)
秋と言えば…
2016年10月18日
こんにちは。朝晩の冷え込みが身体に応える季節になってきました。ところでみなさんは秋と言えば何を連想するでしょうか。食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋、読書の秋・・・様々ありますが、私にとっての秋は「食欲の秋」。したがって私の体重は日々順調に増加しております。そして毎年この季節になるとダイエット商品に手を出してしまい、買ってからは後悔を繰り返すのです。みなさんもこのような経験はありませんか?・・・おそらく私だけでしょうね(笑)
そこで今年は「芸術の秋」に着目してみました。(←やはりダイエットする気がない)。先日、札幌の勉強会に参加してきたのですが、時間に余裕もあったので近くの美術館に立ち寄り“エッシャー展”を観覧してきました。聞き覚えのない名前ですが、“だまし絵”で有名な画家です。彼の作品の特徴は、現実にはありえない錯視的空間を精密に描いております。
左側の「水路」は見たことがあるという方も多いのではないでしょうか。水が循環していますが、よく見るとありえないですね。中央の「階段」も有名です。少し見づらいですが螺旋状の階段が永遠に続いています。右側の絵は、一瞬だけでは特に違和感なく見えますが、上階と下階がありえない連結をしており、柱の遠近感もおかしなことになっています。不思議ですよね!しかし、よ~く考えてみてください。そもそも絵は2次元なので何も不思議なことは起きていないのです。問題は人間の脳にあります。人間は3次元の世界で生きているので、平面であっても立体的に見ることができるよう脳が発達しました。したがって、平面を立体的に認識しようと補正するのです。奥行感や遠近感なども脳が勝手に作り出しているわけですね。そのほうが脳にとっては都合が良いらしいのです。つまり、「錯視」は、このような脳の特性を利用しているのです。この他にも多数の錯視絵が展示されており、私の脳はすっかり騙されてしまいました。改めて人間の脳の複雑さを体感。
そして、ある日お風呂に入ろうとした時のことです。ふと鏡に映った自分のお腹に目をやると、ありえない構造をしていましたが、錯視ではなく現実でした(笑)
(文:理学療法士主任 渡邉)春の健康診断で思ったこと
2016年07月28日
こんにちは。今年の夏はカラッと晴れた日が少ないですね。休日は昼からビールを飲みたい私にとっては少々物足りない夏となっています。これからの巻き返しに期待です。
さて、題名にもあるように少し前に春の健康診断の結果が出たのですが、血液データを見た瞬間目を疑いました。中性脂肪:1000・・・?基準値がおおよそ150未満と言われている中性脂肪がまさかの4桁。これは医療関係者としてマズイ、いや、それ以前に人間として大丈夫なのか?そんな思いに駆られました。
すぐに中性脂肪について調べたところ、中性脂肪が高くなる原因はざっくり言うと食べ過ぎ、飲みすぎ、運動不足とのこと。確かにすべて当てはまっていましたし、この1年で体重が5キロ以上増えていたのも事実。さらに、中性脂肪が高いことによって引き起こされる病気について調べたところ、動脈硬化による心筋梗塞、脳梗塞と肝機能障害による肝硬変などが挙げられていました。もう、完全に目が覚めましたね。まず毎日の晩酌をやめ、お酒は飲み会の時だけにしました。次に脂質を抑えるために肉は主に鶏肉を食べるようにし、炭水化物を抑えるためにお米に白滝を混ぜて炊くようにしました。さらに脂質、炭水化物、たんぱく質のすべてを抑えるために野菜を中心に食べることにしました。
ここまでは何とか出来たのですが、運動不足の解消がなかなか難しい。仕事終わりに運動する元気はないし、休みの日にわざわざ運動したくない。しかしそんなことを言っていても始まらないので、とりあえず晴れた休みの日に五稜郭公園をランニングしてみました。その後家に帰りふらっと体重計に乗ると、なんとピーク時より4キロ体重が減っていました。試しに次の日もランニングしてから体重計に乗ると前日より500グラム減少。これだけ結果が出ると楽しくなり、休みの日はランニングが日課に。この調子で秋の健康診断までに中性脂肪をせめて200前後まで落としたいと思います。昼からビールもしばらく我慢ですね…。次回、秋の健康診断の結果を報告します!!
(文:作業療法士係長 村上)
地域包括ケアシステムという言葉をご存知でしょうか?出前講座の
2016年06月13日
6月に入りました。北海道には梅雨が無いと言われますが、ぐずついた天候が続いております。ですが、我々西堀病院リハビリテーション課は雲のような暗い表情を見せず、雨のような汗を流し日々奮闘しております!(笑) 4月から入職した新人たちも少しずつリハビリテーションの世界を学び始めております。
さて、話は変わりますが、地域包括ケアシステムという言葉を皆さまはご存知でしょうか?病気やケガをした時、今までは病院への入院、リハビリを通してご自宅へ復帰されるという流れが一般的ではなかったでしょうか。この地域包括ケアシステムというのは、入院されてリハビリを通し退院される前、退院されてからの患者さまが自分の暮らしたい場所で生き生きと生活していけるよう患者様のご家族様や介護サービス施設(通所リハビリや訪問リハビリ)、ケアマネージャーさんたちと連携を密に取り、充実した生活を送っていけるよう支援していくシステムのことです。
私たち西堀病院はこの地域包括ケアというキーワードを念頭に置き、そしてリハビリテーション課としても地域包括ケアシテムの構築に向けた取り組みを実施しております。課内に地域包括ケア委員会というものを設立し、院内スタッフへの意識づけや転倒予防教室などの予防事業に加え、リハ課独自の取り組みとして「出前講座」という取り組みを実施していきます。当院圏域内だけではなく、圏域外の地域にも転倒予防教室や体操指導などを希望されるご施設さま、町内会、学校もあるかと思います。そんな時は、是非、当院リハビリテーション課へご相談ください。私たちリハビリ専門職が専門的な知識を持って、皆さまの健康のためにできることをさせていただきたいと思います。
(文:理学療法士係長 佐藤)